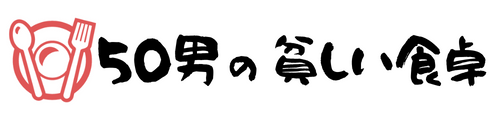見渡す限りの田畑(でんぱた)の中に、ポツンと建ついわくありげな石碑。車でビュンビュン走っている時には気にならないのだけれども、ゆっくり歩いているときに見かけると、なんだか気になったりするもの。
いったい、アレは何の意味があるのだろうと調べてみると……
首塚でしたぁ!!

比較的新しいものなら刻まれた文字を判読できるのだけれども、この石はかなり古そうで、そもそも文字が刻まれていたのかどうかも怪しい。

近づいてみても文字や記号の痕跡すら見つけられないほどに風化しています。

裏側もまたしかり……一体だれが何のために建てたのだろう!?
しかし僕は知っています、この石碑が何を意味しているのかを……いや、この地域に住んでいる人なら結構しっているのかな。
この石碑は戦国時代の激戦地「槍戦場」と呼ばれた場所、古戦場に建つ首塚だったのです。
「龍造寺vs大友」荒平城攻城戦

僕が訪れているのは福岡県福岡市、戦国時代は筑前の国の中心的な役割を果たした地域。そしてここ早良区の南部地域は、肥前佐賀と国境を接する最前線でした。
戦国時代末期ごろ、この地は豊後(大分)の大友氏が支配していました。そして荒平山の中腹から山頂にかけて築かれた安楽平城を本城とし、付属する3つの峰に出城を配した堅固な山城で守りを固めていたのです。
そこへ1579年、筑肥国境を分かつ背振山地を越え、筑前の支配をもくろむ肥前佐賀の龍造寺隆信が攻め込んできます。安楽平城攻城戦の始まりです。
安楽平城は援軍を受けて約半年の籠城戦を戦いますが、最後は援軍とともに城主自ら敵陣への攻撃を敢行。この野戦で城主と嫡男が討たれ、城兵と将のほとんどを野戦で失った安楽平城は開城して降伏しました。


また一説によるとこの戦いで城主は討ち死にするも、嫡男は城に撤退して立花山城の道雪から援軍を受けて籠城。第二次安楽平城攻防戦で落城したという説もあります。
首塚は僧兵たちの首を葬った場所

今回紹介する首塚は安楽平城攻防戦の最終局面、城主の小田部鎮元が自ら軍勢を率いて出陣した馬立原の戦い、その前哨戦となった野戦で討たれた「大日堂の山伏たち」の首塚です。

もともと大日堂の山伏たちは小田部氏と友好関係にありましたが、龍造寺の侵攻を受けて敵方に寝返ります。

その結果、小田部氏の居城である安楽平城の搦め手と隣接していた大日堂と、その軍事拠点である池田城が攻撃され、共に戦った山伏や地侍たちは大将である大教坊と共に全滅。その時に討ちとられた八十五の首を埋めた場所に首塚が建てられ、今も残されていたのです。

山伏や地侍を率いて戦った大教坊の墓は池田城があった山の麓、現在の大日堂敷地内にあります。
なぜ寺が攻められたのか疑問に思う人もいるかもしれませんが、戦国時代の寺は寺領という領地を持っていました。そして領地を守るために武装し、僧兵や地侍などを従えて有力な武装勢力となっていました。
その武装勢力が侵攻してきた敵方に寝返った、しかも場所は城の目の前です。隙があれば排除されるのは当然、でなければ敵方の先鋒として攻めてくる可能性もあるのですから。

大教坊を討ち取って大日堂と池田城を攻め落とした小田部勢の士気は上がり、そのまま龍造寺の本陣である本城という付け城へ進軍を開始。

しかし、大日堂の火の手を見て小田部の城兵が討って出たことを察知した龍造寺軍は、ただちに軍勢を整え大日堂の救援と、迎撃に向かいます。
龍造寺の本陣から出陣した先鋒が大日堂へ急行、この動きが龍造寺本陣に向かっていた小田部勢の退路を遮断する形となり、大日堂と龍造寺軍本陣の本城との間に合った前線陣地、馬立山の麓で龍造寺の迎撃部隊と小田部勢が激突。

戦勝の勢いに乗る小田部勢でしたが、兵力で勝る龍造寺軍の迅速な対応により包囲されてしまい、総大将の城主小田部鎮元、その嫡子九朗と共に八丁川で討ち死に、壊滅しました。
この野戦で城兵と将の多くを失った安楽平城にもはや戦う力はなく、開城したと伝わります。

この戦いで勝利した龍造寺の兵たちが、鎧や太刀についた血を洗い流したと伝わる場所があります。今は多々良瀬と呼ばれる場所、大刀洗いの瀬がなまったのだそうです。
さらに、この近くに小田部勢の首を埋めたと伝わる首塚、千人塚とよばれる場所があるとのことですが、残念ながら見つけることができませんでした。
安楽平城物語によると、今は首塚のあった場所に2軒の家が建っているとのことでしたが……

ということで、偶然に田んぼの中にポツンと建つ石碑の正体を知ってしまった僕。
図書館でいろいろと調べたうえで、こうして古戦場を歩くのはすごく楽しかった。お金もかからないしね。
さらに言うと、歴史好きの人なら安楽平城跡に登ってみるといいかもしれない。僕もまだ写真を始めていなかった頃に二つのルートから行ったことがあって、結構人気の登山スポットというか、石垣なんかも一部残っているし、切岸や堀切、曲輪と土塁跡なんかがガッツリわかるので見ごたえのある戦国山城跡なんです。